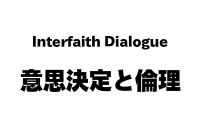![]()
―2007年5月7・8日 ドイツ、チュービンゲン
アブラハムを始祖とする三つの一神教
―歴史的大変動と今日の挑戦
チュービンゲン大学名誉教授
ハンス・キュング
序
私たちは、一般化された疑念という脅威に直面している。今回はユダヤ人ではなくムスリムが対象だ。あたかも、彼らの全てがその宗教に扇動され、暴力の潜在性があると見られている。それとは対照的に、クリスチャンは、その宗教に教えられたが故に、全て非暴力的であり、平和であり愛がある-それは素晴らしい-と見られている。
もちろん、特に多くのムスリム少数民族を抱えるヨーロッパには、多くの問題がある。しかし、もっと公平になろう。もちろん、民主主義憲法国家の市民は、結婚の強制、婦人の抑圧、名誉のための殺人、その他古代の非人間的慣習を「人間の威厳」という名の下で拒否している。しかし、ほとんどのムスリムもこれには同調しているのである。彼らは、何の識別もなしに非難が「ムスリム」および「イスラム」全体に対して向けられていることに苦しんでいる。彼らはイスラム教の忠実な市民でありたいが故に、私たちの描く「イスラム」として自分たちを認めていない。
私たちは公平になろう。誘拐、自爆テロ、車両爆弾、首切りなど、少数の過激派が行うことを「イスラム」の責任とする人々は、同時に米軍が行った刑務所での残忍な処遇、空爆、戦車攻撃など(イラクだけでも数万人の市民が殺害されている)、そしてパレスチナにおけるイスラエル占領軍のテロリズムを、キリスト教とユダヤ教の責任として非難すべきである。戦争開始から三年、米国市民の多数は、中東とその他の地域における石油と覇権の戦いを「民主主義のための戦い」と「テロとの戦い」と装う人々が、世界を欺いているのだと認識している。しかし彼らは成功したわけではない。
2003年のチュービンゲンでの第三回グローバル倫理講義において、国連のコフィー・アナン事務総長は次のように強調した。「いかなる宗教も倫理システムも、その信者の一部が道徳的な過失を犯したからといって非難されてはならない。例えば、もしもクリスチャンである私が、十字軍や異端者弾圧の行動によって、私の信仰を判断されることを望まないのならば、少数のテロリストがある宗教の名で犯す行為をもって、他人の信仰を判断することにも極めて慎重であるべきだ。」
そこで皆様に尋ねたい。より深刻な悲惨さしかもたらさないこの報復行為を私たちは続けるべきなのだろうか、と。
否。暴力と戦争へのもうひとつの基本的な姿勢が要求されているのだ。そして基本的には、いずこであろうと人々はそれを望んでいる。ただしアラブ諸国や時には米国でも、権力亡者や盲目的政府によって横道にそらされ、メディアのイデオローグやデマゴーグによって思考力が鈍ってしまう場合もある。
三日月や十字架の旗の下で暴力が振るわれてきた。後者は、十字架という和解の印を、ムスリムやユダヤ教との戦いの徴に歪曲してしまった中世や現代の「十字軍」である。キリスト教もイスラム教も歴史的には各々の領域を攻撃的に拡大していき、それぞれの権力を暴力で防衛してきたのである。その領域では、平和ではなく戦争のイデオロギーを普及させてきた。したがって、問題は複雑である。
私たち全員は、膨大な情報に殺到され、私たち自身の姿勢を失う危険に直面している。時には、宗教学者ですら、彼らの学問分野でも、木ではなく森を見ることが困難になったという見解を表明している。そこで、例えば社会学では細分化された研究に専念し、広い文脈で考えなくなっている。あるいは考えられなくなっている。ここで私は、変化を受け入れるために新たな範疇が必要だと考える。
そこで、この一時間にアブラハムを始祖とする三つの宗教、すなわちユダヤ教、キリスト教、イスラム教の特定の基本的方向性を説明したい。議論のポイントは、三つの絡み合う質問を提示することである。
すなわち、(1)不動の中核と基盤、つまり無条件に温存されなければならないものは何か?(2)画期的大変化、すなわち変わり得るものは何か?(3)今日の挑戦、すなわち私たちがなさなければならないものは何か? である。
1.不動の中核と基盤
これは極めて実際的な質問である。私たちの宗教それぞれでは何が無条件に温存されるべきなのか。この三つの一神教全てにおいて、極端な立場が見られる。ある者は、「これだけは温存されるべきだが、それ以外はない」と言い、他の物は「全てが温存されなければならない」と主張する。
完全に世俗化したクリスチャンは「温存されるべき物など何もない」と言う。往々にして、彼らは神も神の子も信じず、教会を無視し、説教や聖餐式なしで生活している。キリスト教の文化的遺産│欧州の教会やヨハン・セバスチャン・バッハ、正教の礼拝式の美学、あるいは矛盾していても確立された秩序の柱としての教皇│を大切にするくらいがせいぜいだろう。それでも彼らは教皇の性的道徳や権威を拒否し、時によっては懐疑主義者や無神論者となる。
しかし完全に世俗化したユダヤ人も「温存されるべき物など何もない」と言う。彼らはアブラハムと先祖の神のことなど何とも思わず、彼の約束を信じず、ユダヤ教の礼拝堂での祈りや儀式を無視し、超正統派をあざ笑う。彼らはしばしば彼らのユダヤ教に代わる近代的代替宗教を見出してきたが、それには宗教色はない。それはイスラエル国家でありホロコーストの訴えである。これはまた、世俗化したユダヤ人にとってユダヤ人としての帰属意識と連帯を生み出すが、往々にして同時にアラブ人への国家的テロを正当化し、それ自体が人権を軽蔑することである。
そして完全に世俗化したムスリムもまた「温存されるべき物など何もない」と言う。彼らも神を信じず、クルアーンを読まず、彼らにとってムハンマドは預言者ではなく、シャリーア(イスラム教の法律)を拒否する彼らにとって、イスラム教の五本柱も何の役にも立たない。宗教色がないので、イスラム教を、政治的イスラム主義、アラブ主義、民族主義の道具として利用するのがせいぜいといったところである。
この「何も温存する物はない」という立場への反動として、その正反対「全てを温存せよ」を耳にする。全てがそのまま残るべきだと。「カトリック教義の何一つも壊されてはならない。さもなければ、全てが崩壊する」とローマの伝統主義者たちは声を大にする。「ハラハー(ユダヤ法)の一語も無視してはならない。神の意思が各言葉の裏にあるのだ」と超正統派ユダヤ人は抗議する。そして多くのイスラミストのムスリムたちは、「クルアーンの一言も無視されてはならない。それぞれが神の言葉だからである」と主張する。
お分かりのとおり、いずこでも紛争は先にプログラム化されているのである。これは三つの宗教に限られたことではないが、特にこの三つの宗教で顕著なのだ。こうした主張が戦闘的あるいは攻撃的になされる所では、極端な立場同士でしばしば衝突が起きる。
しかし、現実はさほど暗くはない。ほとんどの国で、政治的・経済的・社会的要因に圧倒されていなければ、極端な意見は多数派とはならない。常に、国と時代によりその規模は異なるが、自らの宗教に関しては往々にして無関心ないし無知ではあっても、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の信仰とその生活を放棄しない人々が、ほとんどの国に常にかなり多く存在している。他方、彼らは全てを維持する意図もない。多くのカトリックは、ローマが教える全ての教義や道徳を受け入れてはいない。多くのプロテスタントも聖書の全てを文字通り受け入れていない。多くのユダヤ教徒もハラハーの全てに従うわけではない。そして多くのムスリムもシャリアの命令を厳密に守ってはいない。
とはいえ、最近の歴史的形態とその表現を見ず、各宗教の聖典│旧約聖書、新約聖書、クルアーン│を考察すると、各宗教で不動な物が、単に存在する物と同一であるのみならず、これらの中核や本質をなすものは、聖典により定義され得るのである。それで、ここでの質問はかなり実質的である。私たちの宗教それぞれにおいて、不動な正当性のあるもの、そして恒常的に不動な要素は、何であるべきなのかということである。すべてが温存される必要がないことは明瞭であるが、温存されるべきは、信仰の中身なのである。それぞれの宗教の中心であり基盤である法典であり、信仰なのである。それはヨハネス23世が第2回ヴァチカン会議の開会式で述べられた。そこには私も親友のヨーゼフ・ラッツィンガー(教皇ベネディクト16世)も十代の神学生徒として参加していた。より具体的な質問には簡単に基本的な答えを出そう。
問1 キリスト教はその魂を失わないよう、何が温存されなければならないか?
答 いかなる歴史的、文学的、社会学的な聖書論評が批判、解釈、矮小化されようとも、新約聖書における信仰の中心的内容は救世主そしてアブラハムの神の子であり、今日でも同じ神の精霊を通して存在するイエス・キリストである。「イエスは救世主、主、神の御子である」という告白なしにキリスト教は存在しない。イエス・キリストという名前が新約聖書の動的中心であり、これはいかなる意味でも静的に理解されるべきではない。
問2 ユダヤ教がその本質を失わないためには、何が温存されなければならないのか?
答 いかなる歴史的、文学的、社会学的な聖書論評が批判、解釈、矮小化されようとも、ヘブライ聖書の中心的内容は、唯一の神とイスラエルの人々である。「エホバはイスラエルの神であり、イスラエル人は彼の人々である」という告白なしに、イスラエル人の信仰もヘブライ聖書もユダヤ教も存在しない。
問3 文字通り「神への服従」のイスラム教として残るためには、イスラム教で何が温存されなければならないのだろうか?
答 クルアーンの異なるスーラ(章)を収集し、秩序立て、編集するプロセスがいかに面倒であろうと、全てのムスリム信徒にとってクルアーンが神の言葉であり聖典である。たとえメッカのスーラとメディナのスーラ間の相違にムスリム教徒が気付き、これらの啓示を解釈に取り入れようとも、クルアーンの中心的メッセージは完全に明瞭である。「神の他に神はおられず、ムハンマドがその預言者である。」
ユダヤ教の真髄は、イスラエル人の神との特別な関係である。キリスト教の出発点は、イエス・キリストの神および父との特別な関係である。そしてイスラム教の中核をなすものは、クルアーンの神との特別な関係であり、それがイスラム教を構成し具現化しているのである。イスラム教の歴史ではかなりの紆余曲折があったものの、これがイスラム教の基本的概念であり、決して放棄されるものではない。
三つの一神教の温存されるべき顕著な特徴は、それぞれが共有しながらもそれぞれを際立たせているものである。
ユダヤ教、キリスト教、イスラム教が共有するものは何だろうか? アブラハムの単独唯一の神、慈悲深い創造主、全ての人間の保護者であり裁判官でもある神である。歴史や個人の人生についても循環的な見解ではなく終局的志向、預言者の重要性、基準的な聖典と共通の倫理基準があげられる。
それでは彼らを際立たせるものは何だろうか? ユダヤ教にとってはイスラエルが神の民であり土地であること。キリスト教にとっては、イエス・キリストが神の救世主であり子であること。そしてイスラム教にとってはクルアーンが神の言葉であり聖典であることなのである。
常にユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教の中心にあるものは、次のことに根付いている。
- 最初からのオリジナリティ
- 数十世紀の歴史を通した継続性
- 言語、人種、文化、民族国家の相違には関わらない帰属意識
しかし、この信仰の中心、基盤、実質は抽象的な隔離状態の中で存在し続けてきたわけではない。歴史的には、これは時代の変遷に伴い、何度となく再解釈され実施されてきたのである。トインビーは「挑戦と応戦」と言った。神学者や歴史家、その他の学者にとって、制度的・神学的なものを歴史的・年代順の説明と組み合わせることが重要である。それなしに制度的・神学的なものに説得力のある基盤を与えることはできない。
2.画期的大変化
時代の新たな画期的な事件の集合-社会全般、宗教コミュニティ、信仰の宣告、信心-の考察などが、三つの宗教で再三台頭し、この唯一かつ同じ中心を再解釈し具現化してきた。ユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教において、この歴史は異常に劇的であった。世界史が常にもたらした新たな大挑戦への応戦として、宗教コミュニティ-キリスト教とイスラム教の場合は、最初は小さかったが急速に拡大した-は、一連の宗教的変遷を見た。事実、長期的に見ると、革命的なパラダイムの変更ともいえよう。私はこの概念を歴史家トーマス・クーンの『科学革命の構造』(1962年)から学んだ。コペルニクス革命で何が変わったのか。太陽、月、星は変わらなかったが、私たちが変わったのだった。私たちが天体を見る目、私たちの世界観、すなわちパラダイム(理論的枠組み)が変わったのである。特定のコミュニティで共有された信仰、価値観、技術等の集合が変わったのである。私はこのパラダイムの変更をまず教会の歴史に適用し、その後、異なる宗教に適用した。宗教改革で何が変わったのか。神とキリストとクリスチャンの精神は変わらなかった。しかし、信徒の見解、パラダイム、規範が変わったのである。
宗教のパラダイム-マクロ・パラダイムないし画期的な集積の全体-の歴史的分析は知識に方向性を与える。パラダイムの分析は、基本的な定数と決定的な変数に同時に集中することで、偉大な歴史的構造と変遷を組み立てることを可能にする。こうして、世界史における変化と、それから出現する特定の宗教の画期的な基本モデルを説明することが可能となる。
そこでこのような長い歴史を背景に、画期的な集合全体の歴史的・制度的分析を試みなければならない。私は自著『キリスト教』の中で、キリスト教史のマクロ・パラダイムを作り上げた。
1 初期キリスト教のユダヤの終末論的パラダイム
2 古代クリスチャンのギリシャ正教的パラダイム
3 中世のローマ・カトリック的パラダイム
4 宗教改革時代のプロテスタント的パラダイム
5 理性・進歩志向の近代的パラダイム
6 近代後の世界的パラダイム?
第一の洞察 どの宗教も、過去が常に今日と同じだったという静止した存在ではない。むしろ、どの宗教も、異なる画期的な集積を経験した、生き、そして発展している現実である。第一の決定的な洞察は、パラダイムが今日まで生き延び得たという点であり、これはユダヤ教にもイスラム教にも重要なことである。これは「正確な」自然科学と対照をなす。例えばプトレマイオスの古いパラダイムは、数学や実験のおかげで経験的にその正偽が証明され得る。例えば、コペルニクスのような新パラダイムを使う決定は、長期的には証拠により「強要」し得る。しかし、宗教(そして芸術)の分野では異なる。信仰、道徳、儀式の問題において、何も数学や実験で決定されるものはない。そこで宗教界では、古いパラダイムが消滅するとは限らない。むしろ、それは新パラダイムと数世紀も共存し続け得るのだ。(宗教改革や近代性という新しいものが、初期教会や中世の教会という旧いものと共存できたように。)
同様に、ユダヤ教の歴史におけるマクロ・パラダイムも左記のように作成した。
1 国家形成前の部族的パラダイム
2 王国時代のパラダイム
3 追放後のユダヤ教である神政政治的パラダイム
4 ラビとシナゴーグの中世的パラダイム
5 同化という近代的パラダイム
6 近代後の世界的パラダイム?
第二の洞察 異なるパラダイムへの固執と対抗意識は、宗教の状況を評価する上で最重要である。これが第二に重要な洞察である。何故か? 今日まで同じ宗教を信じる人々は、異なるパラダイムの下で暮らしてきた。それらはその時代の基本的条件に形成され、特定の歴史的メカニズムに左右される。例えば、今日でも精神的には13世紀を生きている(トマス・アクィナス、中世の教皇、絶対的教会の秩序と同時期)カトリック信者たちが依然として存在する。ギリシャ正教の代表者で精神的には4〜5世紀(ギリシャ正教の父たちと同時期)を生きている人たちもいる。そしてプロテスタントでも、コペルニクス以前の16世紀(コペルニクスやダーウィン前の宗教改革者たちと同時期)を生きることが依然として規範である人たちがいる。
ユダヤ教とイスラム教のパラダイム変化を見ると、この固執が確認できる。ユダヤ教徒もイスラム教徒も異なるパラダイムの下で暮らしているのである。同様に、一部のアラブ人は、依然として偉大なる「アラブ帝国」を夢見ており、単一アラブ国家(パン・アラビズム)という形でのアラブ人の団結を望んでいる。他方、アラビズムではなくイスラム教が人々を結びつけることを優先させ、パン・イスラミズムを望んでいる人々もいる。そして超保守的なユダヤ教は中世のユダヤ教に理想を見出し、近代国家であるイスラエルですら拒否している。対照的に、多くのシオニストたちは、数十年しかもたなかったダビデとソロモンの王国の国境内の国家のために努力している。
最後に、2006年10月にオックスフォード大学から発行された私のイスラム教に関する著書『ワン・ワールド』でも、イスラム教の歴史におけるマクロ・パラダイムを示した。
1 初期のイスラム教社会のパラダイム
2 アラブ帝国のパラダイム
3 世界宗教としてのイスラム教の古典的パラダイム
4 ウラマーとスーフィーのパラダイム
5 近代化のイスラム的パラダイム
6 近代後の世界的パラダイム?
第三の洞察 この永続する質、旧い宗教のパラダイムへのこの固執と敵対意識が、まさに今日の宗教内・宗教間の紛争の主な原因に違いないし、異なる趨勢、政党、緊張、紛争、そして戦争の主たる原因のひとつに相違ない。この第三の重要な洞察は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教に対する核心的質問を提示する。それは、それぞれの宗教がその中世(少なくともキリスト教とイスラム教には「偉大なる時代」に思えた)にいかに反応し、三つの宗教それぞれが防御を強いられている近代にいかに反応するのかである。宗教改革の後、キリスト教はもうひとつのパラダイム変化を経験した。それは啓蒙の時代である。ユダヤ教は、フランス革命とナポレオン戦争後に初めて啓蒙を経験し、その結果少なくとも改革派ユダヤ教は宗教改革も経験した。しかしイスラム教はいかなる宗教改革も経験せず、今日まで近代性とその中核的価値である意識と宗教の自由、人権、寛容、民主主義という点においてもかなり特別な問題を抱えているのである。
3.今日の挑戦
近代的パラダイムを認める多くのユダヤ教徒、クリスチャン、ムスリムは、旧いパラダイム下で暮らす同じ宗教の信者たちとよりも相互にうまく付き合っている。対照的に、中世の虜であるカトリックは、例えば性道徳に関しては、イスラム教やユダヤ教の中世的要素を持つ人々と連携し得る。(1994年カイロで開催された国連人口会議で見られたように。)
和解と平和を望む人々は、批判的あるいは自己批判的なパラダイム分析を回避するわけにはいかない。それによって初めて次のような質問に答えが出せるのである。キリスト教(もちろん他の宗教でも同じ)のどこに定数があり、どこに変数があるのか? どこに継続性が見られ、どこに不連続性があるのか? どこに合意があり、どこに抵抗が見られるのか? これが四番目の洞察である。温存されなければならないものは、何よりも宗教の本質、基盤、中核であり、それからその原点によって与えられた定数となる。キリスト教精神への恒常的信仰や禁欲主義の法は、変数である。必ずしも温存されなくとも良いものは、原点から鑑みて必要ではないもの全て、種ではなく殻、基盤ではなく構造であろう。全ての異なる変数は、必要とあるならばあきらめられる(あるいは逆に形成できる)ものなのである。
したがって、とりわけ顕著なグローバル化の時代における全ての宗教的混乱の中で、パラダイムの分析は、グローバルな方向性に向かうことの手助けともなる。現在が国際関係、西側とイスラムの関係、そしてアブラハムを始祖とする三つの宗教間の関係を再構築するやっかいな最終段階にあることは間違いない。選択肢は明瞭となってきた。宗教間の敵対意識・文明の衝突・民族間の戦争か、あるいは文明間の対話・民族間の平和かである。全ての人類への恐ろしい脅威のなかで、憎悪・復讐・敵意の新たなダムを建設するのではなく、私たちは、偏見の壁の石をひとつずつ取り外すことによって、対話の橋、特にイスラムへの橋を築くことができるのである。
4.普遍的倫理に貢献する三宗教
この橋作りにとって、この三宗教がそれぞれ異なっていても、また、数千年紀をかけて変遷してきたそれぞれのパラダイムもやはり異なっていても、倫理のレベルではこのような橋作りを可能にする定数があることが決定的に重要である。
人類は、動物から進化したなかで、非人間的でなく人間的な態度をとることを学んだ。しかし進化したにもかかわらず、人間が持つ欲望のために、彼らの中の猛獣は現実として残っている。そして人間は非人間でなく人間であるよう努力し続けざるを得なかったのである。
したがって、全ての宗教、哲学、イデオロギー的伝統において、今日まで最重要として残った単純な人間性の倫理的責務がある。
•「汝、殺す、虐待する、傷つける、強姦するなかれ」もしくは肯定文では「生命を尊重せよ」である。これは非暴力と全ての生命を尊重する文化への誓約である。
•「汝、盗む、搾取、汚職するなかれ」あるいは肯定文では「正直に公平に対処せよ」は連帯と公正な経済秩序の文化への誓約である。
•「汝、嘘をつく、騙す、偽造する、操作するなかれ」もしくは肯定文では「真実を話し誠意ある行動をせよ」は、寛容の文化と真実の生活への誓約である。
•「汝、性的不道徳を犯す、伴侶を虐待する、辱める、蔑むなかれ」あるいは肯定文では「相互を尊敬し愛せよ」は平等な権利と男女間のパートナーシップの文化への誓約である。
ヨガの創始者でもあるパタンジャリ、仏典、ユダヤ教聖書、新約聖書、クルアーンに見られるこれら四つの倫理的責務は、次の二つの基本的な倫理原則に基づいている。
○まず第一に「黄金律」と呼ばれるものがある。キリストの数世紀前に孔子が組み立てた概念で、全ての大宗教や哲学的伝統でも知られているが、当然のものとはなっていない。この「自ら欲さないことは、他にもしない」は初歩的なものではあるが、多くの困難な状況で決断を下す際に有用である。
○黄金律は人間性の規則でも支持されており、全く同意反復的なものではない。「若くとも高齢だろうとも、男女を問わず、障害者・非障害者を問わず、キリスト教徒だろうが、ユダヤ教徒だろうが、ムスリムだろうが、全ての人間が人間的に扱われるべきである。」これは人間性とは不可分なのである。
これから明らかなことは、共通の人間倫理ないし普遍的倫理は、アリストテレス、トマス・アクィナス、あるいはカントのような倫理体系ではなく、人間と社会の個人的な道徳的確信を形成する初歩的な倫理価値、基準、態度なのである。
もちろん、こうした倫理は事実に反する。その人間性の絶対的要請は、演繹的に満たされるものではないが、時々思い起こし、認識しなければならないものである。しかし、コフィー・アナンが二〇〇三年のチュービンゲン大学におけるグローバル倫理の講義で語ったように「しかし、もし特定の信仰や価値体系の信徒の発言や行動を非難することが間違っているのならば、特定の価値は普遍であるという概念を受け入れない人々がいるからというだけで、それらを放棄することも間違っているに相違ない。」
国連事務総長がその講義で使った結論を私もここで使いたい。「私たちは依然として普遍的価値をもっているのだろうか。もちろんである。しかし、それを当たり前と思ってはならない。」
•普遍的価値は慎重に思考される必要がある。
•普遍的価値は防御される必要がある。
•普遍的価値は強化される必要がある。
そして私たちは、私たちが宣言する価値に従って、個人的にも社会的にも世界の中でも生きる意思を私たち自身の中に見出さなければならないのである。
政治家と倫理規範
― 「国際政治における要因としての世界宗教」
OBサミット専門家会議終了後の講演
インターアクション・カウンシル名誉議長
ヘルムート・シュミット
まず、親愛なるハンス・キュング教授に感謝申し上げます。私は、1990年代の初期からグローバル倫理プロジェクトに注目してきましたので、この招待を受けることをとてもうれしく思いました。「グローバル倫理」という言葉は、ある人々にとっては、あまりにも野心的に聞こえるでしょう、確かに、その目標、あるいは解決すべき任務は、真にそして必然的に極めて野心的です。この時点で、五大陸から集合した元大統領、首相たちが、インターアクション・カウンシル(OBサミット)として1987年以降世界共通の目標を打ち立ててきたことに言及しても多分よいでしょう。しかし、私たちの作業は、相対的にまだ小さな成功しか収めていません。対照的にハンス・キュングと彼の友人達の作業は卓越しているのです。
私自身、偉大な宗教に共通の道徳律を考えるよう、鼓舞してくれた敬虔なムスリムに感謝しています。四半世紀以上前、当時のエジプト大統領アンワール・アル・サダトが、アブラハムを起源とする三つの宗教に存在する多くの類似点、特に呼応する道徳律の共通ルーツを、私に説明してくれました。彼は例えば、ユダヤ教の旧約聖書の詩篇、キリスト教の山上の説教、イスラム教のクルアーンの第四節における平和に対する共通の戒律も知っていました。彼は、もしも人々がこの収斂を認識していたならば、あるいは少なくとも政治指導者たちがそれぞれの宗教の倫理的相似点を知っていたならば、永続的平和は可能であると信じていました。彼はこの点については固い確信を抱いていたのです。数年後、エジプト大統領として、自らの確信に呼応する政治的行動に出た彼は、四回の戦争で敵国だったイスラエル国家の首府と議会を訪問し、和平を提案し締結させました。
私のように高齢になると、両親、兄弟、多くの友人の死を経験します。しかし、宗教過激派によるサダトの暗殺は、他の喪失よりも深く私を動揺させました。私の友人サダトは、平和の戒律に従ったために暗殺されたのです。
後でこの平和の戒律に戻りますが、まずは但し書きです。一つのスピーチ、しかも一時間以内に限定されたもので「政治家の倫理」というテーマをカバーなどしきれません。この理由から今日私は、まず政治と宗教の関係、次に政治における理性と良心の役割、そして最後に妥協する必要性とそれが必然的にもたらす厳格さと一貫性の喪失について語らざるを得ないのです。
Ⅰ.
さて、平和の戒律に戻りましょう。平和の格言は、政治家に絶対的に要求される倫理または道徳の不可欠な一要素です。それは、国家とその社会における国内政策にも、対外政策にも平等に適用されるのです。この他にも法則や格言はあります。それには当然、世界中の宗教が教え、要求する「黄金律」が含まれます。エマニュエル・カントは、彼の道徳律において、黄金律を単に再形式化したに過ぎません。それは、一般的には「自分にして欲しいと思うことを他人にもなせ」と表現されています。この黄金律は全ての人に適用され得るのです。私は、他の人々とは異なる基本的道徳の規範が政治家に適用されるなどとは全く思っていません。
しかし、普遍的道徳性の中核をなす規範以下のレベルでは、特定の職業や状況には、多くの特別な規則があります。例えば、医者たちに尊敬されている「ヒポクラテスの誓い」、あるいは裁判官の職業的倫理、あるいは実業家、金貸しないし銀行家、従業員もしくは戦争中の兵隊などに要求される特別な倫理規定もあります。
私は哲学者でも神学者でもないので、特定の政治倫理の概説や法典を提示し、プラトンやアリストテレスや孔子たちと競争することなど試みるつもりは毛頭ありません。2500年もの間、この偉大なる哲学者たちは、政治倫理のあらゆる要素や成文を収斂させ、時には高度な論議をかもし出してきました。近代ヨーロッパでは、マキァヴェリあるいはカール・シュミットからユーゴー・グロティウス、マックス・ヴェーバー、そしてカール・ポパーにまで広がっています。他方私は、政治家そして政治的編集者としての人生から│ほとんどが自国において、そしてそれ以外は近隣諸国や遠い国との対応から│私自身が学んだ洞察を皆様に提示することに限定せざるを得ないのです。
この時点で、神とキリスト教の議論はドイツ国内問題ではかなり稀有ですが、他国の政治家との議論や交渉ではそうではなかったという私自身の経験を指摘したいと思います。フランスとオランダでEU憲法の国民投票が行われた時、両国の多くの国民にとって、EU憲法が神への言及を十分にしていないことが反対の決定的な動機でした。政治家の大多数は、憲法の文章で神を引用することを控える方を選びました。ドイツの憲法である基本法では、その序文に「神の前での責任を意識して」と神が表現されており、第五六条には宣誓の言葉として「神の助けがありますように」と再び神が出てきます。しかし、その直後に基本法は「宣誓は、宗教的確約なしに行ってもよい」としています。いずれにせよ、神がカトリックかプロテスタントの神であるのか、ユダヤ教ないしムスリムの神であるのかは、個人の決定に任せてあるのです。
基本法の場合、政治家の大多数がこの文章を支持しました。民主主義の秩序においては、法の支配の下で、特定の宗教的信仰や文章よりも政治家と彼等の理性の方が、憲法政策においては決定的な役割を果たしているのです。
最近、ヴァチカンが数世紀を経てやっと、かつて政治闘争にも利用されたガリレオの合理性に対する評決を覆しました。今日、私たちは中東の政治勢力と宗教勢力が、いかに人々の精神を巡って流血の争いに閉じ込められており、私たち全員が備えている理性、合理性がいかに繰り返し無視されているかを毎日目撃しています。2001年に、何人かの宗教過激派が、彼等の神に奉仕していることを確信して、ニューヨークで3000人の命と共に、自らの命も終らせた時に、「神の不在」でソクラテスに死刑判決が下されてからすでに2500年も経過していました。明らかに、宗教と政治そして理性の間の絶え間ない対立は、人間の条件の永続的要素なのでしょう。
Ⅱ.
ここで私は個人的経験を加えても良いかと思います。私は、ナチスの時代に成長しました。1933年の初め、私は14歳になったばかりでした。私は8年間の兵役につきましたが、戦争中は「もしも全知全能なる神がおられるならば、この様な惨事を許される筈はない」と思っていました。そして、予想された大惨事に続く戦後の時代において、キリスト教会に希望を繋いでいたのです。しかし1945年に、私は教会が道徳を再確立することも、民主主義と立憲国家を再構築することもできないことを経験しました。私自身の教会は、依然として「より高き権力に従え」というパウロのローマ人への書簡でもがいていたのです。
むしろ、最初はヴァイマール時代の経験豊かな政治家たちが、新たな出発で重要な役割を果たしました。アデナウアー、シューマッハー、ヒューズたちです。しかし、連邦共和国の出発点では、高齢のヴァイマール時代の政治家ではなく、ルードヴィッヒ・マクシミリアンの信じ難い経済的成功と米国のマーシャル援助が、ドイツ国民を自由と民主主義、そして立憲国家の支持に回したのです。
この真実を何も恥じることはありません。結局は、カール・マルクス以降、私たちには経済的現実が政治的確信に影響を及ぼすことが分かっていたのです。この結論は半分ほどしか真実ではないかもしれませんが、統治する権力が産業と労働に十分な秩序が保てなければ、全ての民主主義が危険に瀕するという事実は残っているのです。
その結果、私は、道徳的のみならず政治的にも経済的にも、教会の影響力に失望し続けました。私が首相を務めた頃から4半世紀を経て、私は多くの新しいことを学び、多くの著書を読みました。その過程で、私は以前知らなかった他の宗教や哲学に関して、若干の知識を得ました。そしてこの教育が私の宗教的寛容性を強化させたのです。同時にそれは、私とキリスト教との距離を広げました。しかしながら私は、私自身をキリスト教徒と称し、道徳的退廃に対抗し、多くの人に支援を提供している教会にも籍を残しております。
Ⅲ.
キリスト教の神への言及に関して、今日でも私を悩ませ続けていることは、キリスト教そして他の信仰でも見られる│何人かの宗教家、政治家の間でだが│他を排除する傾向です。すなわち、「あなたは間違っているが、私は啓蒙され、私の確信と目的は神に祝福されている」という見解です。私たちの異なる宗教やイデオロギーが、全ての人が良くなるための努力を阻止するなど許されてはならないことは、私には長年明瞭でした。つまり、私たちの道徳的価値が、実に類似しているからなのです。私たちの間で平和は可能ではあっても、カントが言ったように、私たちは常にこの平和を再構築し「確立」しなければならないのです。
もしも各宗教の信徒たちや聖職者たちが、他の宗教の信徒たちを帰依、改宗させようとすると、平和の目的には役立ちません。このため、信仰の宣教の裏にある基本的な概念に対する私の態度は懐疑的なのです。ここでは、私の歴史知識が特別の役割を果たします。すなわち、キリスト教とイスラム教双方が、数世紀におよぶ誓約、信念、理解からではなく、剣、征服、支配によって広められた事実のことです。中世の政治家たち、すなわち公爵や国王、カリフや教皇は、宣教的思考を充当させて自らの力を拡大する手段に変え、その目的のために数万人の信徒たちを志願させたのでした。
例えば、キリストの名において兵士たちが聖書を左手に持ち、剣を右手に持った十字軍は、私の目には実際には征服のための戦争と映ります。近代では、スペイン、ポルトガル、英国、オランダ、フランス、そして最後にドイツがアメリカ大陸、アフリカ大陸、アジア大陸のほとんどを奪うために暴力を行使しました。道徳的、宗教的優越性を確信して、これら外地の大陸を植民地化したのかもしれませんが、植民地帝国の確立は、キリスト教とはほとんど関係なかったのです。むしろ、これらの行為は権力と自己中心的な利益のためになされました。あるいは、イベリア半島のレコンキスタ(再征服)を例にあげてみましょう。これもキリスト教の勝利のためだけではなく、その中心にあったものは、カトリック教徒の君主、フェルディナンドとイザベラでした。今日インドで、ヒンドゥー教徒とムスリムが闘う、あるいは中東でムスリムのスンニ派とシーア派が闘っている場面でも、最重要な点は権力と支配であり、宗教と大衆に影響力のある聖職者たちがその目的のために使われているだけなのです。
今日、21世紀の初めにおいて、宗教に動機づけられた、あるいは宗教を装った世界的な「文明の衝突」の本当の危険が発生しています。近代化された世界の一部では、宗教を装った権力の動機が、貧困への道理ある怒りや他の人々の裕福さへの羨望と交じり合っています。宣教的動機が、権力への過剰な動機と混合しているのです。この文脈で、バランスも取れ、自己規制された理性の声が注意を惹くなど困難です。狂喜し、興奮した大衆のなかでは、個々の理性への呼びかけなど全く聞こえません。今日、完全に尊敬に値する民主主義と人権に関する西側のイデオロギーと説教が、全く異なる習慣の下で発展してきた文化に対して、宗教的熱狂と軍事力で押し付けられていることについても同じことが言えるのです。
Ⅳ.
私自身これらの経験から一つの明確な結論を導き出しました。すなわち、自分が属する宗派を、自らの権力への願望のための道具にしてしまう政治家、大統領、あるいは首相を信用しないこと、したがって次の世界を志向しがちな宗教と現世界の政治を混合させる政治家とは距離を持つこと、です。
この警戒は、国内・海外の政治に等しく適用され得ます。これはまた、各国の市民と政治家にも等しく適用されます。私たちは、他の宗派、教団の信徒をも尊重し、彼らに寛容であるべきだ、と政治家に要求しなければなりません。政治指導者としてこうした能力のない人は、平和-私たちの国内の平和であっても、他国との平和であっても-にとってはリスクとして見なされねばならないのです。
全ての宗教でラビ、神父、牧師、ムーラ、アーヤトッラーが、他の宗教に関する知識を私たちから隠してきたことは、悲劇です。むしろ、彼等は他の宗教を非難する風潮で考え、軽蔑さえするように私たちに教えてきました。しかし、宗教間の平和を望む人は誰であろうと、宗教的寛容と尊敬を説教すべきなのです。他に対する尊敬には、彼等に関する最低限の知識が必要なのです。私は、三つのアブラハムを伝統とする宗教の他に、ヒンドゥー教、仏教、神道も同じ尊敬と同じ寛容を求める権利があると長年確信してきました。
この確信のために、私は、世界宗教者会議による「グローバル倫理シカゴ宣言」を歓迎し、それが望ましいだけでなく、緊急に必要なものであると見てきました。同じ基本的立場から、今から10年前にOBサミットは、日本の故福田赳夫の主導で練り上げた「人間の責任に関する世界宣言」案を国連事務総長に提出しました。全ての主要宗教を代表する人々の助けを借りて起草されたその宣言は、人間の基本的な原理をついています。ここで、私は特にハンス・キュング教授に対し、彼の支援に感謝を表明したいと思います。同時に私は、ウィーンのケーニッヒ枢機卿による貢献も感謝をもって思い起こします。
Ⅴ.
しかし私はまた、2500年前、ソクラテス、アリストテレス、孔子、孟子等の後世に多大な影響を及ぼした人類の教師たちが、表面的には誉めたものの、宗教を必要としなかったことも理解しています。彼らにとって、宗教は彼らの仕事の周辺的なものでしかなかったからです。彼らに関して私たちが知っていることから想像すると、ソクラテスは彼の哲学の基礎を、孔子は彼の倫理の基礎を理性のみにおいていたことが分かります。彼らの教えのどこにもその基礎を宗教においてはいません。しかし両者とも、今日ですら数百万、数千万の人々の道標なのです。ソクラテスなしにプラトン│おそらくエマニュエル・カントもカール・ポパーも│は存在しなかったでしょう。孔子と儒教なしに、中国文化およびその歴史的継続性と活力が世界史でも独特な「絹の王国」が存在し得たかは想像しがたいのです。
ここで、一つの経験が私にとって重要です。明らかに、その創始者が神、預言者、聖典あるいは特定の宗教に帰依せず、自らの理性のみに従ったとしても、卓越した洞察や科学的功績を創出することは全く可能であり、また倫理的・政治的教えも然りであるということです。このことはまた、社会・経済そして政治における功績についても同様に適用され得ます。しかし、私たちが住んでいる世界において、この経験が受け入れられるよう「突破」するには、欧米の啓蒙運動の数世紀におよぶ苦闘があったのです。ここでは、「突破」という表現が科学、技術、産業に関しては正当化され得るでしょう。
他方、政治に関しては、不幸にして「突破」と言う言葉は、啓蒙主義には僅かしか当てはまりません。自らを「神のおかげ」の国王と見なしたヴィルヘルム2世であろうと、神に祈願する米国大統領であろうと、政治においてキリスト教の価値を引用する政治家であろうと、彼等は自らがキリスト教徒であることに宗教的に縛られています。人によっては、キリスト教徒としての宗教的責任ある立場にあると、単純かつ明らかに感じているでしょうし、ほとんどのドイツ人が今日そうであるように、この責任を相対的には漠然としか考えていない人もいるでしょう。多くのドイツ人は、結局はキリスト教から距離をおいているのです。多くの人々が教会を去り、神と別れてしまった人達もおりますが、彼らが依然として善人であり良き隣人であることに変わりはないのです。
Ⅵ.
大多数のドイツ人は今日、ある重要で基本的かつ拘束力のある政治的信念を共有しています。何よりも、彼等は不可侵な人権と民主主義の原則にコミットしています。この内面的なコミットメントは、明らかに個々の信仰や不信心とは関係なく、その二つの原則のいずれもがキリスト教の教義には含まれていない事実とも関係ありません。
キリスト教のみならず他の世界宗教やその聖典も、主として信徒たちに法や義務を強制してきましたが、個人の権利となると聖典のどこにも見つからないのです。他方、私たちの基本法の最初の20条は、ほとんど全て個人の市民の憲法上の権利に言及していますが、彼等の責任や義務にはほぼ何も言及していません。私たちの一連の公民権リストは、ナチス統治下の個人の自由に対する極端な抑圧への健全な反応なのです。それはキリスト教やその他の宗教の教えに基づいたものではなく、全てが私たちの憲法において明確に表明されている一つの基本的価値「不可侵な人間の尊厳」に基づいているのです。
同様に、第一条では、議員であろうと政府当局者であろうと官僚であろうと、あるいは連邦政府、州政府、地方自治体であろうと立法府・行政府・司法府は、法律が直接適用可能とする基本的権利に拘束されています。同時に政治家は、基本法が良いあるいは成功する政治と同様に、貧弱な政治と成功しない政治にも余地を与えていることから、広範な行動範囲をもっています。このため、私たちは憲法への遵守に関しては、議員や与党が必要であるのみならず、第二に裁判所による彼らへの規制と、第三に有権者と世論による政治の規制を必要としているのです。
もちろん、政治家は過失を犯しがちであり、事実間違いを犯します。結局は、彼らも他の市民同様、同じ人間的弱点をかかえ、世論と同様の弱点も持っているのです。時には政治家は、自発的に決定を迫られることもありますが、ほとんどの場合は決断を下す前に、いくつかの選択肢とそれぞれの結末を考慮するために、複数の人からアドバイスを受ける十分な時間と十分な機会が与えられています。政治家が固定的論理やイデオロギー、所属する政党の権力への固執に流されることを自らに許せば許すほど、識別可能な諸要因と個別の事例における自らの決断の結末を比較、考慮しなくなり、過失、間違い、失敗の危険も増大します。このリスクは、決断が自発的になされる時、とりわけ高まるのです。いずれの場合も彼はその結末に対する責任を負っており、この責任は往々にして、実に重荷となり得ます。多くの場合政治家は、憲法問題、宗教問題、哲学や理論に関する決断を下す時、手助けを得られないし、自らの理性と判断力に依存する以外ないのです。
このために、マックス・ヴェーバーが1919年に行った「職業としての政治」と題された、未だに読み応えのあるスピーチで、政治家の「バランス感覚」について語った部分が若干一般的すぎたのです。彼は、政治家が「自らの行動には説明責任」を持たなければならないと付け加えました。事実、私は一般的結果のみならず、特に意図されない、あるいは受け入れられた後遺症も正当化されなければならないと信じています。政治家の行為の目的は道徳的に正当化されなければならず、彼の手法も同様に倫理的に正当化されなければなりません。この「バランス感覚」はまた、不可避で必要とされるいかなる自発的決定に対しても十分でなければなりません。しかも、もしも考慮する時間が十分にあるのならば、慎重な分析と熟慮がなければならないのです。この格言は、極端で劇的な場合になされた決定に適用されるのみならず、税務や労働政策などの通常・日常的法案にも適用されます。そしてまた、新規の電力発電所や新しい道路に関する決定等にも適用されます。例外なしに適用されるのです。
換言すれば、政治家は理性に訴えたのでなければ、自らの行動とその結末を良心的に直視できないということです。良き意図や名誉ある確信のみで、彼らの責任の重荷を軽減することはできないのです。この理由から、私は常に、究極的結果の倫理と対照的な責任の倫理の必要性を説いたマックス・ヴェーバーの言葉を的確だと思ってきました。
しかし同時に私たちは、政界入りする多くの人が、理性ではなく彼らの確信によって動機付けされていることも知っています。同様に私たちは、国内問題でも対外問題でも、ある決定が理性的熟慮からではなく、人々の確信からなされることも認めなければなりません。そして私は、選挙民の大多数が誰に投票するかという選択を、時のムードに影響される感情に基づいて決めていることにも、何の幻想も抱いていません。
しかしながら私は、政治的決定における二つの要素-理性と良心-の重要性について過去何十年もの間、講演や原稿を通して語ってきました。
Ⅶ.
この結論がいかに単純かつ不明瞭に聞こえ、また見えたとしても、民主主義の現実からすると、さほど単純ではないことを、私は付け加えなければなりません。民主主義政府において、一人の人間が政治的決断を下すことは、実際には例外的です。圧倒的多数の場合、一人の人間ではなく、国民の大多数が決定するのです。これは、法案についても例外なく真実です。
議会において多数を達成するためには、数百人が法案の内容に合意しなければなりません。同時に、相対的には重要ではないことが複雑化し、対処を困難にすることもあります。この場合、著名な専門家や所属する政党の公認された指導者に頼ることは簡単ですが、ある点に関して数名の議員が異なるが根拠のしっかりした見解を紹介するという事例も多くあり、それは重要なことなのです。彼らに同意してもらうためには、彼らの見解を取り入れなければなりません。
つまり、法案と議会の多数による決定とは、これらの個人たち全員が妥協する能力と意思を持たなければならないのです。妥協なしに多数合意は形成され得ません。原則として、妥協できないあるいはその意思のない人は、誰であろうと民主的法案には用はないのです。確かに妥協は、政治的行動の厳格さや一貫性の喪失を往々にしてもたらします。しかし、議会の民主的議員には、その類の損失を受け入れる意思がなければならないのです。
Ⅷ.
同様に、妥協は国家間の平和を維持するための外交政策においても常に必要です。例えば今日米国政府が育成しているような国家の聖域的利己主義は、長期的には平和裏に機能しません。
数千年におよぶ、アレクサンドロスからカエサル(シーザー)、チンギス・ハンからピサロあるいはナポレオンそしてヒトラーやスターリンに至るまで、平和の理想は外交政策の実施において、ほぼ決定的な役割を担いませんでした。それはまた同様に、理論的な政府の倫理あるいは政治への哲学の統合においても、ほぼ何の役割も担ってきませんでした。逆に、数千年の間、そしてマキァヴェリからクラウゼヴィッツに至るまで、戦争は政治の要素として当たり前に思われていたのです。
オランダ人のユーゴー・グロティウスやドイツ人のエマニュエル・カント等の少数の哲学者達が、望ましい政治的理想として平和を今日の地位に押し上げました。ヨーロッパの啓蒙運動までは、数十世紀かかったのです。しかし、一九世紀を通じて主要欧州諸国にとって、戦争は政治の異なる手段として続き、20世紀も同様でした。人々は、戦争を人類の重要な悪であり、回避されるべきものとして見てきました。この見解が東西の指導的政治家にも共有されるには、二つのおぞましい世界大戦まで必要だったのです。こうした動きは、国際連盟を設立する試みと今日も存在する国際連合の創設に見られます。それはまた、米ソ間の均衡を意図した軍縮協定や、1950年代以降の欧州統一、そして1970年代のドイツのオスト・ポリティーク(東方政策)などにも見られます。
ところで、ボン政府の対モスクワ、ワルシャワ、プラハのオスト・ポリティークは、平和政策の決定的要素の顕著な事例です。すなわち、平和のために行動したい政治指導者は、向こう側の政治指導者(つまり潜在的敵)と話さなければならず、相手の言い分も聞かなければなりません。語り、聞き、可能ならば妥協するのです。もうひとつの事例は、平和のための妥協産物だった1975年の欧州安全保障協力会議の最終声明(ヘルシンキ宣言)です。ソ連は東欧国境線の不可侵性に関する宣言を西側の指導者たちから獲得し、西側は人権について共産主義の国家元首たちから署名を獲得しました(これは、後にバスケット・スリー合意として有名になりました。)その15年後のソ連崩壊は、ありがたいことに、外部からの軍事侵入によるものでなく、権力を広げすぎたシステムの内部崩壊だったのです。
その逆の負の事例は、イスラエル国家によるパレスチナとそのアラブ近隣諸国への数十年におよぶ戦争と暴力行為です。いずれも相手と話し合わなければ、妥協と平和は単に幻想的希望として終わってしまうのです。
1945年以来、国際法は国連憲章という形で、国家間の問題に軍事力で外部から介入することを禁止してきました。この基本的規則への例外として、安全保障理事会のみに決定権が与えられているのです。例えば、イラクへの軍事介入は、ましてや虚偽に基づいたものは、確実に非介入の原則違反であり、国連憲章に対する破廉恥な蹂躙です。多くの国の政治家が、この違反について非難されなければなりません。同様に、多くの国(ドイツも含む)の政治家は、人道的立場から国際法に反する介入に責任を負っています。例えば、十年以上に及んだバルカン半島での暴力的紛争(ベルグラード爆撃を含む)は、西側の人道主義というマントの裏に隠されてきました。
Ⅸ.
しかしながら、私は外交政策へのこの脱線から離れて、議会での妥協に戻りたいのです。私たちの開かれた社会では、世論形成に多大な影響力を持つマスメディアは、時には政治的妥協を「馬の交換」ないし「怠惰な」妥協として扱いますが、時には、彼らは政党の非道徳的な規律とされるものに激怒しています。他方、世論形成の過程を批判的に精査し続けることは良いことであり、有用ではありますが、同時に妥協の民主的必要性という定理もその信憑性は続くのです。結局は、個々の議員がそれぞれの利益をかたくなに守る議会は、国家を混乱に陥れます。同様に、個々の議員がかたくなにそれぞれの判断に固執すれば、政府は統治不可能に陥ります。どの閣僚も、どの議会政党もこれを知っているのです。全ての民主的政治家は、妥協しなければならないことを知っているのです。妥協の原則なしに、民主主義の原則はあり得ないのです。
しかし、現実的には、悪い妥協もあるのです。例えば、第三者あるいは将来の世代を犠牲にする妥協です。現在の問題を実際には解決していないのに、解決しているかのごとくの印象を与える不誠実な妥協もあります。こうして妥協という必要な徳も、単なる日和見主義の誘惑に直面することもあります。世論あるいは世論のある要素に迎合する妥協への誘惑は、日常茶飯事として繰り返し見られます。このため、妥協する意思のある政治家は、自らの良心に頼らなければなりません。
自分の良心に反することから、政治家が行ってはならない妥協もあります。こうした場合、唯一の選択肢は、公に反対を表明することであり、場合によっては唯一残された道は辞任か落選です。自らの良心に反することは、自身の名誉と道徳そしてその人間の個人的高潔さへの他人の信頼をも傷つけるからです。
しかし、良心の過失もまたあります。自らの理性もしくじることがありますが、良心も然りです。このような場合、道徳的非難は正当化されませんが、恐ろしい損害を被ることもあるのです。またこのような場合、政治家は後に自分の過失を認め、真実を語るべきか否かの質問に直面します。このような状況では政治家は、ここにいる私たち全員がするように、あまりにも人間的な行動に出る。すなわち、公的に良心の過失を認め、私たち自身に関する真実を語ることは、私たち誰にとっても困難な行為なのです。
Ⅹ.
真実に関する質問は、マックス・ヴェーバーが政治家の三つの卓越した特質のひとつであると認定した情熱と、時には対照的です。真実に関する質問は、民主政アテネで2500年前に最も重要な芸術のひとつであると認められ、ある意味では今日のテレビ社会ではさらに重要性を増したレトリックの才能とも対照をなします。選ばれたい人たちは、選挙民に対し、彼らの意図やマニフェストを提示する。そうすることによって、特にテレビの視聴者にアピールしたい場合、後に満たすことができないような約束をする危険に陥ります。選挙に出る者たちは皆、誇張の誘惑にかられるのです。名声への競争そして何よりもテレビの視聴者へのアピールが、昔の新聞購読社会に比較すると、この誘惑を強化してしまいました。
私たちの近代大衆民主主義は、かつてウィンストン・チャーチルが言ったように、私たちにとっては│時に試してみた他の政治形態に比較すると│最善の政府の形ではありますが、決して理想的な形態ではない。大衆民主主義は、過失と欠陥を伴いながら、大きな誘惑に必然的に悩まされます。決定的に残されているものは、暴力や流血なしに、選挙民が政府を変えられるという事実であり、この理由からも議会で過半数を後ろ盾に選ばれた人々は、選挙民に対して自らの行動について説明責任があるのです。
Ⅺ.
マックス・ヴェーバーは、情熱とバランス感覚の他に、政治家の第三の特質が責任感であると信じていました。ここで質問なのですが、誰に対する責任なのでしょう。私にとっては、選挙民は、政治家が答えなければならない究極的権威ではありません。選挙民は往々にして、極めて一般的で流行を追う決定を下し、頻繁に感情や気まぐれに基づく選択をします。しかし、彼らの多数決は、政治家の服従を伴うのです。
私は、良心に関する多くの神学的・哲学的見解があることを認識しておりますが、私にとっての究極的権威は私自身の良心なのです。この言葉は、すでにギリシャ・ローマ時代に使われていました。後に、パウロや他の神学者たちは、神と神が命じた秩序を意識すること、そして同時にこの秩序への違反は罪であると私たちが意識することを意味して、この良心という言葉を使いました。キリスト教徒のある人々は、「私たちの内部におられる神の声」について語ります。私たちの良心に関する理解は、聖書の教えがヘレニズムの世界と接触したことから出現したということを、私の友人リチャード・シュレーダーの著書で読んだことがあります。他方、彼の一生を通して、エマニュエル・カントは、宗教の役割を考慮せずに、彼の良心の基本的価値を考えなかったことはなかったのです。カントは、良心を「人間の正義を内面的裁判所が意識すること」と説明していました。
人間が、良心とは人の理性からくるのか、神に由来すると信じるか否かは別として、いずれの場合も、人間の良心の存在についてはほぼ疑問の余地はありません。キリスト教徒であろうと、ムスリムであろうと、ユダヤ教徒であろうと、懐疑主義者であろうと、自由な考えの持ち主であろうと、成人した人間は良心を持っているのです。そして、どちらかというと小声で付け加えたいのですが、私たちは一度以上自らの良心に反する行動をとったことがあります。私たち全員が「罪悪感の中で」暮らさざるを得なかった時期もあったのです。もちろん、このあまりにも人間的な弱点を政治家も共有しているのです。
Ⅻ.
今日私は、職業政治家として得た30年の体験から学んだいくつかの洞察を皆様に説明しました。もちろん、これらは、多層にわたる現実から抽出した極めて限られたものです。最後に、二重の洞察が私自身にとって極めて重要です。まず、私たちの開かれた社会と私たちの民主主義は、多くの不完全と欠陥に悩まされており、全ての政治家が依然としてあまりにも人間的な弱点をもっていることです。現実的に存在する私たちの民主主義が純粋な理想であると考えるのは危険です。しかし、第二に、私たちドイツ人には、大惨事をもたらした私たちの歴史のために、私たちの全ての力を持って民主主義にしがみつき、民主主義を恒常的に活性化させ、民主主義の敵とは常に立ち向かうあらゆる理由があるのです。このことに合意できて初めて、私たちの国歌の「結束、公正、自由」が正当化され得るのです。
孔子の論語
ハーバード大学・北京大学名誉教授
杜維明
序
論語は、数十年にわたり孔子(紀元前551-479)と弟子たちとの間で交わされた一連の対話から、豊かで変化に富み、自由闊達な時節に適う、そして生き生きとして覚えやすく、示唆に富んだ中身を抽出したものに違いない、と私は考える。論語は、孔子と最も身近にいて、豊富な知識を身に着けた2世代にわたる弟子たちの手によって編纂されたのだろう。だが、弟子たちは編纂した論語を完結品にしようとは思っていなかっただろう。むしろ、彼らの狙いは、論語を世間に知らしめ、その解釈に対し新たな貢献を招くためだったのかもしれないのである。もちろん、彼らが慎重かつ思慮深く項目を選んで編纂したことは明らかだ。こうした弟子たちがとった戦略的理由を推測することは難しくはない。編纂の目的が、弟子たちが懐かしみ、敬慕し、尊敬し、愛して止まなかった模範的な人柄の師の思い出を残すことだったと仮定してみよう。彼らが取り得る編纂方法はいくつかあった。例えば、師の最も重要な活動を時代順に記録し、感謝を込めた伝記を共同執筆し、師の思想の核心部分を記録することもできただろう。だが、彼らは極めて個人的な様式を選択し、師が本当はどのように話し、行動し、考えたか、また個別の質問にいかに生き生きと対応したかを記録した。それは見事に結実した。
古典として、論語は変更可能なオープン・エンド型で、新たな内容や多様な用語、異なる注釈や新たな解釈を付け加えるのに適している。原点は元来、絶えず広がる論語に貢献したい者たちの洞察を受け入れるようになっているのだ。論語は孔子の発言に帰することができる豊富な識見を収められる余裕が十分ある、公的な空間のようである。歴史的文献に記録されている論語には、異なって編纂されたものが少なくとも三種類ある。子曰くで始まる膨大な孔子の発言が、前秦時代(紀元前3世紀)に大量に散在しているが、これらの信憑性に慎重かつ厳しい見方をする学者もいる。懐疑派の影響を受けたこうした用心深い学者は、論語に記されている孔子の発言さえ疑わしいと見なしている。記録として残っている孔子の発言が、孔子本来の言葉を基に新たに作られたのではないか、そして孔子の思想を本当に反映しているのだろうかという疑念が中国研究者の間で広がっている。孔子が何も語ってはいないので、本来の孔子の言葉探しは、少なくとも中国研究者の間では、学問的優先事項になっていた。
状況は1992年、湖北省郭店での竹簡の発見により劇的に変わった。考古学者や文献学者が初めて見せられた竹簡には、第一世代に属する孔子の弟子たちに関する一次資料や、古典に対する孔子の発言という驚くべき記録が残されていたのだ。論語の信憑性は大幅に高まった。礼記にあるような、その他の孔子の発言とされるものも、師の本物の声として聞こえるのだ。孔子の教えが直近の弟子たちを通して、中庸の著者と推定される孫まで伝わっていく輪郭も明らかになった。また、編纂されたと思われている論語に対しては、もはや謎と見なす流れはなくなった。弟子たちの認識に基づく孔子のイメージについて絶対的な確信があるわけではないが、我々が扱っているのは、でっちあげの追想集ではないことを、かなりの自信を持って言える。
現在の論語は、長きにわたる学問的探究によってその内容が深められたものだが、言語学的、文献学的、文学的及び原典研究が蓄積した賜物である。それが多くの賞賛と非難、活用と誤用、評価と批判、理解と誤解をもたらしてきた。確かに、論語へのアプローチには複数あるが、その可能性が無限にあるわけではない。論語には、興味深い解釈をする者と同等に多くの妥当な解釈があるという示唆は、最善でも実行不可能な誇張である。事実、何世紀にもわたり伝承されてきた論語の注釈で、生き残ったのはほんの僅かで重要なものだけだった。解釈する方法は複数あるが、相対主義的な方法論は理論と実際のどちらの面でも機能しない。しかしながら、疑いなく論語は、多様で根本的に異なる読み方さえ許してしまう柔軟性がある文献である。
対話形式
論語は、新約聖書やソクラテスの対話のように、恩師の教えを直接見聞きした経験を大切にした者にとっては、インスピレーションの源なのだ。何人かの学者が指摘するように、論語の第十篇では、身なりや歩き方、目上の者への接し方から、見知らぬ者との出会いや友の歓迎のしかたなどに関する孔子の作法が、繊細で微妙な描写で示されている。事実、孔子の表情、仕草、とりわけ礼儀作法が実に生き生きと描かれているのだ。孔子が教えた日々の手順は、個々の特定の状況における妥当性を示している。彼の弟子たちの目には、彼の優雅な美的感覚が掻き立てられた。孔子は抽象的な宇宙主義よりはむしろ、暮らしてきた具体的な世界の中で、生々しく蘇る。2500年以上たっても、敏感な耳には彼の心の声がいまだに聞こえ、彼の存在感さえ感じさせる。孔子の活気に満ちた個性、そして実際彼の人間性が生き生きと現れてくるのだ。
対話形式は、熟考に基づく会話や凝縮された説話として論語全体に広がっている。先生としての孔子は、表面的には単に弟子の質問に答えるだけだった。弟子たちは師を仰ぎみて、指導、洞察、英知を求めた。そこにはやり取りをする余地などほとんどなかった。相互に言葉を交わすコミュニケーションは、まったく存在しなかったように見える。弟子が師の話の前提に異議を唱えることなどほとんど見受けられないのだ。弟子の子路との場合ですらそうだった。さる問題のある高貴な女性を訪問すると師が決めた時、子路は明らかに不快感を隠さなかった。それでも、師は「自分は何一つ間違ったことはしていない」という抗議以外、何も語っていないのである。[6―28]おそらく弟子たちは、孔子の存在に対する畏怖の念が強かったので、ひたすら師の指導に熱心に耳を傾けていたのだろう。顔回の場合がここでは妥当な例だ。師は次のように言った。「私は顔回と一日中話していることができる。彼はなにも異議を唱えない。愚かにさえ見える。だが、一人の時の彼を見るが良い。彼の行動は師から学んだことを完全に反映しているではないか。そうなんだ。顔回は愚か者じゃない。」[2―9]孔子の弟子として最も尊敬されている顔回は、師としての孔子に対して尊敬の念に溢れていた。
顔回はため息混じりにこう言った。「私が師の教えを熟考すればするほど、越えるべきハードルは高くなるのです。深く掘ればほるほど、抵抗も強くなる。目の前にあったかと思うと、突然それは後ろに廻ったりする。師は人を一歩一歩罠にかける方法を本当に良くご存知です。師は私を書物で刺激し、礼で私の行動を抑制なさる。私が止めたかったとしても、できなかったでしょう。私のエネルギーを全て使い果たしても、目標は私の上に高くそびえたっているのです。私はそれを抱きしめたいのだが、そこへ至る道筋がみつけられないのです。」[9―11]
これら二つの発言の根底をなしているものは、単なる言葉による教えではなく、模範的な教えの方が弟子たちに自己実現の道を見出させられ得る、という仮定的論理なのである。議論は奨励されておらず、引き裂くような言葉は、めったに、有徳の印にはならない。[1-3]「雄弁が何の役に立つと言うのか。機敏な話しぶりは多くの敵を作る。」[5―5]事実、感情的で卑屈な発言といった上辺だけのものは避けるべきである。[5-25]
人の話を聞く技能は、個人的な知識の蓄積に欠かせないものだが、それは優雅に話をする前提条件として、磨かれなければならない。孔子の教授法はソクラテスのそれとは対照的なもので、経験主義的な理解と無言の認識を重視した。
論語で卓越した特徴である「学ぶ」という意味には、実践と認識が含まれる。それはスピリチュアルな実習である。人は心で学ぶだけではなく、身を持って学ぶのだと。曾子の自己修養に関する省察が、ここでは妥当な例だ。「私は毎日三点を反省する。他人のために動いたとき、私は信頼するに足りたのだろうか? 友との交わりの中で、私は誠実だったのだろうか? 教わったことを実践できているだろうか?」[1-4]そのように認識された「学ぶ」ということは、身を整え、心を啓蒙することを伴う。六芸(礼、楽、射、御、書、数)の実践が明らかに示しているように、心身共に鍛えられることが求められ、学ぶことと思考することは相互に補完しあうべきなのだ。[2-15]
この教育方法には信頼に基づく社会の存在が暗に含まれている。孔子が弟子たちと作り上げた同じ考えを持つ者同士の親交というのは、教育を通じて人間の条件を改善するために捧げられる自発的な繋がりなのである。近代の歴史学者は、孔子に関する伝統的な説明を、師の社会的な役割から捉えて、先哲と解釈している。すなわち、彼は中国で私的な学校を設立した最初の学者であると。孔子以前の数世紀前から為政者が支援する学問所は存在してきたが、師は自己資金で教育を始めた革新的な人間だった。論語の中には、安い授業料についての言及が一回だけある。[7-7]しかし、イエスの弟子たちのように、師の周りに集まってきた弟子たちは、子供ではなく、真実を求める、熱心に人生の意味を探求する大人たちだった。彼らは、師の偉大な洞察力と強い使命感に引き付けられたのだった。彼の光輝く、しかし控えめな人格が、彼らの想像力の源だった。
「黙って知識を蓄積すること。学ぶことへの貪欲さを失わないこと、疲れることなく、人に教えること、これらすべては、わたしにとっては、当然のことなのだ。」[7-2]
教育の目的
孔子の教えには一連の決められた教育課程はなかったろうが、論語には、彼の教育目的が人格を磨くためである、との主張を裏付ける証拠が十分にある。最高の師の影響下で行われる教育の第一義目的が人格形成であることは驚くに値しない。これは何を意味するのか? 新儒学家たちは、次のように解釈する。これは「自身のための学問、心身修養の学問、心身と人間性を磨く学問、人間性と天命を悟る学問、賢人の学問、君子の学問(君子、高貴な人、優れた人、深い学識のある人)」である。孔子は、君子に対する考え方については、数多く言及している。最初は、君子になるための学問は難しそうに見えない。「君子は満腹を求めず、住まいは快適さを求めず、仕事に励み、言葉を慎み、自らの道を正すため、有徳の士を求める。そのような人物は本当に学問を好むと言える。」[1-14]
責任ある人間として自らの身を処する君子の姿を描くことにより、孔子は君子とは、行動の作法ではあるが、同時に存在の在り方でもあると明確にした。「君子は話す時は慎重に、行動する時は敏捷に行うべきだ。」[4-24]「自ら実践することをのみ、人に説く。」[2-13]君子は徳と正義を求め[4-11]、世間との対応では、いつも正義の側に立つ。[4-10]
しかし孔子は「君子は重々しくなければ、権威はなく、その学問は底の浅いものになる。君子は誠実と信義を最も重視し、自分より徳の劣る者とは交わらない。誤った時には、躊躇なくそれを正す。」[1-8]と警告した。ここでは、自己の修養のための学問が妥当な例だ。[14-24]「君子は書により自らの学問を広げ、礼を用いて自制する。」[12-15]「君子はゆったりとして、傲慢にならない。」[13-26]「君子は人々の長所を伸ばすことができる。」[12-16]。「彼に仕えることは容易だが、喜ばせることは難しい。君子は我々の能力以上の事は求めないが、道に従わなければ、満足しないからだ。」[13-25]「子路は師に問いかけた。『君子と呼ばれるには、どのような人物でなければならないのでしょうか?』師は答えて『一方では、真面目で鋭敏な人間だが、他方では朗らかで付き合いやすい人物が君子と呼ばれるに値する。友の間では、真面目で鋭敏、兄弟の間では朗らかな人物のことだ。』」[13-28]
エドワード・シルズは、孔子が近代的概念の礼節の発案者だった可能性に注目する。孔子の考える君子は教養があり、文明化された人物だ。熟達した射手で、乗馬の名手だった孔子は、狩りや魚釣りが好きだったが、彼が温めていた理想的人間像を表現する手段として、芸術的意識を磨くことを選んだ。運動家として、彼は弓を選択した。「君子は争いを避ける。それでも、競争しなければならないなら、弓で腕前を競え。対戦の前や後で酒を酌み交わす際にも、君子はお辞儀をして礼儀正しく務め、対戦中でも紳士として振る舞う。」[3-7]飽くことなき旅人として、孔子は困難で危険な旅をする中で、数多くの勇気を示した。しかし、通常「彼は常に暖かく、親切で、敬意を表し、他の人とは異なった穏やかな人物だった。」[1-10]
孔子が生きた時代は政治的には混乱し、社会の崩壊が進む時代だった。最も影響力のあった政治家のひとりだった周公により丹念に磨き上げられた礼の伝統は、機能不全を起こしていた。覇権を争う国家間では内紛が燃え盛っていた。隠遁者の中には孔子に、現世から退出し、自然とのかかわりの中で、平和で静かな人生を楽しむよう誘う者もいた。孔子はそのような実存的選択には敬意を払うが、自分自身の歩む道を追い求めることを決意した。「私は鳥や獣と仲間にはなれない。私は人間社会の一員ではないのか? そうでないならば、私と仲間になれる誰がいるというのか? もし世界が道に従うならば、改革など必要ない。」[18-6]歴史上の宗教(ユダヤ教、仏教、ジャイナ教、道教、キリスト教、イスラム教)の中で、儒教は世俗と神聖の違いを受け入れなかった点で特異である。
厳密に言えば、ハーバードの重要な本が、孔子は世俗を神聖と見なしていたと描写しているのは誤解を招く。孔子は神聖な場所(教会、寺院、シナゴーグ、修道院、アーシュラム)を観想、瞑想、祈り、礼拝のための精神的に神聖な場所とは捉えていなかった。孔子はまた、聖地や来世を究極的には実存せず、我々が生きている現世から根本的に異なる世界だとは捉えていなかった。人間の条件を内面から変えることに誓約することで、孔子は必然的に当時の政治と関わりを持つことになった。しかし、孔子の本当の職業は政治で、学問ではないと説明するなら、それは誤解を招くことになる。
弟子たちの目には、孔子が時折統治の問題に没頭し、政治的権力を使えないことを懸念しているように映った。もし、支配者に雇われていたならば、明らかに新たな礼に基づく秩序を作り上げる自らの能力には、確実に自信があった。[13-10][17-5]しかし、彼は学者的役人として、君子はどのように振る舞うべきか、ということに対する明確な意識の持ち主で、当時の政治家を軽蔑していた。
弟子の子貢が問う。「君子と呼ばれる行為とはどのようなものでしょうか?」孔子曰く「振る舞いは高潔で、世界の隅々まで外交使節として送られ、君命を辱めない人物が君子と呼ばれるに値する。」「その次の段階の君子は、とお聞きしてもよろしいでしょうか?」と子貢が問う。「一族の間では孝行者と言われ、郷里の村では年長者を敬うと称えられる者だ。」「では、その次は?」「彼の言葉が信用できること。引き受けたことは何でも最後までやりとげること。これでは、ただ単に粗野な男の頑固さを示しているに過ぎないかもしれないが、それでも、程度の低い君子とすべきではなかろうか」「この点で、先生は現在の政治家をどのように評価されますか?」「悲しいことに、この取るに足らない生き物たちは、語るに値しない。」[13-20]
理想的統治力
孔子が本当に天から与えられた才能は教えることではなく、政治だと我々が主張したとしても、彼が政治は倫理の延長だと仮定しているのだから、彼にとっては、個人的道徳を修めることが政治に参加する前提になることを認識しなければならない。この意味で政治は、権力や権威や影響力を操る能力を意味しない。また、権力を得るために戦術や戦略を用いることでもない。むしろ、それは、道徳的なリーダーシップを通じて達成される公正で効果的な統治方法なのである。「徳治は、自ら動くこともなく、多くの星たちの敬意を集める北極星に当たる。」[2-1]
この理想的な統治力を見習い、適切な統治を行うには強制や強要は必要ない。「君子の徳の力は風である。民衆の徳の力は草である。風が吹けば、草はなびく。」[5-8]優しい風に自然にそよぐ草のイメージは、威圧的権力の行使とはつながらない。それは、同じリズムに合わせた祭祀的な舞いのイメージだ。この文脈で考えると、行政サービスは道徳的リーダーシップを明確にする最も効果的手段だが、それだけが、重要な領域ではない。
儒教式の統治の最も目立つ特徴は、家族倫理の政治的意義を中核にすえる。誰かが、孔子に問うた。「先生、政府に参加してはどうですか?」孔子は答えて曰く、「書経によると、考を尽くし、兄弟に優しくすること。即ち、天下に貢献することである。これは政治行動の一つだから、政府に参加する必要はないのだ。」[2-21]
さらに孔子の徳治の理論と実践は本質的に、ちっぽけな生き物による政治活動とは異なった。彼は、彼らの政治ゲームをするほど身を落としたくなかったのだ。彼が政治活動する目的は、「道」を広めることであった。彼が好む方法は、統治や管理の前提として、国家の基本的問題に取り組むことであった。こうした基本的な問題が後回しにされるのなら、その名に値する政治など存在しない。同音異義語を用いて、孔子は政治(政)を正す(正)と定義した。それは政治が主にリーダーシップを意味しているからである。仮に指導者が公職に就くものとして身を正さないのならば、たとえ我々の制度が十分であったとしても、政府の質は劣化し、統治行為は低下する。
彼の有名な「正名」理論は、見た目には単純である。「齊景公が政治について孔子に問うた。孔子は答えて『君主は君主らしく、臣は臣らしく、父は父らしく、息子は息子らしく。』齊景公は『素晴らしい。君主が君主らしくなく、臣が臣らしくなく、父が父らしくなく、息子が息子らしくないとすれば、私は何を信じたらよいのか。日々の食べ物すら信じられないだろう。』」[12-11]十分な食べ物や武器、民の信頼が国の平和と安定に極めて重要であっても、民の信頼が最も不可欠であるとの信念が、この主張には暗黙の内に含まれている。孔子の徳治政治が到達し得ない理想と思われないように、彼は現実的な手段で彼の時代の権力に近づいた。
手短かに言えば、孔子は現実政治に対して、何一つ幻想を抱いていなかった。彼は継続的に全体状況を分析し、政治的任命を得る機会をつかもうと精力的に動いたのだった。孔子は、複雑な政治状況に対応するために十分準備していたし、優秀な弟子たちと一緒に、民衆の暮らしを改善するため、積極的な役割が果たせると考えていた。彼の弟子たちの中に、礼法、音楽、財務、外交、軍事など、国家経営の専門的知識があったのは偶然ではない。しかし、孔子はご都合主義のために自らの信念を犠牲にすることはなかったし、民衆の安寧が思いやりのある政治(仁政)の基本的な正当性である、というこだわりを常に持ち続けた。
孔子が政治家としては成功者でなかったのは明らかに思える。最初は、力のある君主の宮廷では、丁重に、うやうやしくもてなされていたが、彼は影響力を行使できる確実なポストを見付けられず、最後は去らざるを得なかった。彼は主に富と権力しか興味がない輩たちから君主を遠ざけようと試みたが、上手く行かなかった。このことは、孔子が政治的陰謀にはとりたてて才があった訳ではないことを意味している。孔子に同情的な歴史家の目には、悲劇の英雄に映るかもしれない。何故なら、孔子が政治的手腕を発揮する機会が与えられていたならば、彼自身もそう信じていたように、栄光の周王朝時代の政治秩序をある程度は再建できたかもしれない、と信じているからだ。[17-5]しかしながら、彼の自己認識を今日の政治用語で述べることは誤解を招く。その理由のひとつは、政治を「正すこと」として捉える彼の認識には、知識や文化、道徳や審美眼が含まれるからだ。それは、認識論的、倫理的、審美的意味合いを伴う地域社会の構想なのだ。
我々はすでに孔子の観察を引き合いに出しているが、それは、律儀に家族の義務を遂行することが、政治に関与する者の正真正銘の姿だからである。彼の見解では、政治的プロセスとは家から始まるのだ。個人の生き方から政治を切り離すことはできない。孔子の実践スタイルには、自己認識と相互学習を通じた議論に基づく地域社会の創造という意味が潜在的にある。孔子の弟子たちは、人間の条件を改善するための共通の道に参加することを決めた成熟した大人で、世間に積極的に関わる自らの能力については十分認識していた。彼ら集団の団結は、あらかじめ考えられた教育的手本にしたがって、孔子が強制したものではない。また、毛沢東主義者のように、明確に定義された政治的倫理的機能を遂行せんとの堅い決意により形成されたものでもなかった。
むしろ、彼らは博識で教養があり、倫理的にも優れ審美眼のある人物として公益に尽くす潜在能力を開発するため、孔子の周りに集まったのである。こうした建設的な方法により、弟子たちは互いに尊敬しあい、互いに評価しあいながら、自己修養の道を歩むことができたのだ。孔子は弟子たちに用途の決まった道具になるのではなく(2-12)、どのような状況下でも、様々なレベルでの政治的行動がとれる多面的な才能を持った君子(人格者で高貴な身分の人間で、権威があり深い学識のある人物)になるよう勧めた。
孔子と弟子たちの間の交流は、彼らが乗り出した共同作業が中国史上初めてのもので、歴史的な主要宗教の中でも特異なものであったことを示している。孔子は自分が学問的伝統の創始者ではなく、弟子たちにも、その考えを守るように促した。孔子が自らを創始者ではなく、伝達者と述べるのは、謙虚さによるものではなかった。[7-1]孔子はまた、弟子たちに目指すよう教えた仁徳を最大限体現した人物という訳でもなかった。彼が聖人とか、人間性豊かな(仁)人間と言われるのを拒んだのも、謙虚さ故にではなかった。[7-34]しかし、彼の控えめな個人的肖像は、弟子たちに対して畏敬の念を抱かせる存在感を打ち消してしまうものではなかった。彼のひらめきの源は、濃密な人生から生まれて来るものであり、その人生とは特定の瞬間と場所に具体的に位置づけられ、しかも、そこで具現化された中身は、共通して普遍的重要性を持っていたのである。
伝達者としての夢
孔子は、民衆の生存と隆盛の道に対する守護者として自らを見なしていたので、人間の理解を超えた並外れた存在や、あるいは、人間の参加を必要としない自然の進化というよりも、累積されてきた伝統の設計者である聖人やそれに値する人に懇願した。礼楽の精緻な体系を構築することにより周王朝の維持に貢献した周公は、孔子が考える模範とすべき人格の持ち主だった。彼の一生の夢は周公のグランド・デザインを復活させることであり、自己修養と慈悲、正義、責任の道徳的規範に基づく世界平和の新しい時代を迎え入れることだった。周公は、画期的な業績をあげたが、孔子と同じように創案者ではなく伝達者だった。何故なら、聖君であった堯・舜、唐・虞、文・武から偉大な事業を受け継いできたからである。孔子の歴史的認識は、依然として維持されていたかもしれない文化的規範と、そうした使命を果たすために彼は選ばれたという強烈な使命感で形づくられた。
孔子が、彼に夢の実現を可能にする機会を与えてくれる君主を探し求めて、国から国へ放浪している時、おそらく彼は無意識のうちに同じ考えを持つ集団を形成したのだ。それが、前述した討論に基づく共同体である。後から考えると、孔子は彼が理想とする政治を実践する地域を任されたことはなかったが、彼が実際に作り上げた社会的現実は極めて意義深いものだった。孔子と弟子たちで協力して作り上げた共同体は、開かれて柔軟な、意思の疎通がはかれ、対話が盛んで誰でも受け入れる、相互利益をはかる性格のものだった。孔子は、段階的に物の本質を見られるように、体系的に導く哲学者として弟子たちと関わっていたのではなかった。論語には、ソクラテスの対話のような精緻な理論のようなものは何もない。事実、孔子は、単なる言葉による説得力を全く信用せず、饒舌を軽蔑し、言葉巧みな表現を不快に感じていた。彼は、外交における雄弁さや思考における明快さ、そして論文の明瞭さを高く評価したが、顔回の場合のように、効果的な論争法よりも、黙って物事を評価する方を選んだ。効果的な論争法は法律論争、あるいは訴訟の中でさえ使われる策略を彼に思いださせるものだった。民事事件では、孔子は形式的、専断的、強圧的な方法で争いを調整するよりも、交渉、仲介、和解を好んだ。
政治の目的
孔子が描いた理想の社会や彼が例示的に教えることで築きあげた共同体は、自発的な繋がりに基づいていた。こうした繋がりの主な目的は、仲間の自己実現を促す手助けをすることである。このような社会的構想に基づく政治形態は、政治的、知的エリートの反射性と、思いやりのある政治が機能する効果的手順に関連している。役人たちの監督する力は、二つの過程で具体的に現れる。一方では責任感を強く意識し、他方では、民衆の暮らしに影響する政策を良心的に遂行することである。それが注意深く自己修養に努める君主を通じて行われる、と孔子が主張したのは驚くべきことではなかった。農業、飢饉の救済、物質的な問題などの国家の重要課題は、何よりも民衆の福祉を思い、真剣に遂行されなければならない。ヘーゲルの誤解とは反対に、孔子の思想では主権は君主ではなく、民衆の側にあるのだ。実際に、主権は天命によって民衆に与えられている。この意味で、天から一任されている君主は、道徳的な振る舞いをし、民の声に責任を持って答える義務を課せられている。
民衆と認識された人々は、無知でもなければ、無力でもない。孔子以前の時代から培われてきた偉大な伝統によれば、徳の向上こそ、君主が民衆の父や母としての役割を正当化できる理由そのものなのだ。孔子の指導的立場に続いた孟子が主張したように、君主が義務を果たせないのならば、(「君主は君主らしく行動すべき」)、臣下は異議を唱えるべきなのだ。君主が彼らの不満に応えられないのならば、臣下は抗議として職を辞すべきである。異常な状況下では、主君殺しさえ許される。「正名」の考え方によれば、無責任な君主は、力も権威も正当性も欠落した単なる一匹狼以外の何物でもない。彼は、民のために追放されても殺されても構わないとされる。民は水のようであり、船を支えることもできれば、転覆させることもできる。「民が見るように天も見、民が聞くように天も耳を傾ける。」これは抽象的概念なのではなく、実用的な考えで、しばしば実践されてきた。
道徳的力、文化的価値観、社会的結束、歴史認識により政治を変えるという孔子の決意は、政治的秩序の優位性に対する彼のナイーブな情熱だとしばしば誤解されてきた。彼の決意は、政治の究極的目的は人々が栄えることにある、という認識に基づいていたのだ。確かに、政治は権力、影響力、権威と結びついている。しかし、すでに述べたように、政治の目的は教育を通じた倫理である。安全の維持と暮らしを支えること自体は目的でなく、人々が栄えるための条件なのである。「君主から民まで皆、自己修養を根本的なものとして捉えるべき」との孔子の教えは、社会をコントロールするメカニズムを植え付けるためではなく、信頼を基礎とした地域社会の土台を提供するためである、と考えられている。エミール・デュルケームの言葉を借りれば、孔子は相互理解と集団が共有する自己認識を通して、社会の有機的な結びつきをもたらした。孔子の弟子には、知識階級、農民、職人、兵士、商人、その他さまざまな職業を持つ人々がいた。背景の違いや生活志向の多元性による分業体制が、孔子率いる仲間集団を豊かにしたのである。
1950年代に、孔子の考えに潜む民主的精神に触発されたシカゴ大学中国学部長H・G・クリールは、こうした点において、彼をリベラルな民主主義者あるいは合理的な人道主義者と特長づけた。しかし、孔子をそのように分類するのは、時代錯誤ではないにせよ、誇張である。自由民主的な考えは、孔子の世界観において拒絶される可能性すらなかった。しかし、孔子が人間の適切な交わりとして構想したものは、近代的な政治的分類をいかに幅広くとらえたとしても、遥かに超えるものであることに注目することが重要である。我々の分断された関心領域である細分化された専門的訓練の枠組みにおいて、「機械的」な結合よりもむしろ「有機的」結合、普遍的兄弟愛のような結びつきという概念は、単なる想像上の可能性にすぎないように思えてしまう。学問分野の特化と専門性の影響下にある近代学問の理論家たちは、完全性とは、人間が永続的に求めているものと認識することに躊躇する。孔子と弟子たちが築き上げた仲間意識は、人間が共有する憧れが具体的に現れたものにすぎなかった。
精神的旅路
孔子のカリスマ性は、人を引き付ける魅力に潜んでいた。自らのビジョンと使命を共有し合い、世界を内側から変革するため、エネルギッシュな人々からなる多様な集団を魅了したのだ。こうしたことは、自己修養の技能を通じて弟子たちの精神的・肉体的資源を活用することによりなされた。儒教の自己修養は、人間の精神性への個別的探求よりもはるかに複雑で、多元的な次元を持っている。それは、心と体ばかりでなく、人間の存在を取りまく全体的な環境に関係している。孔子自身が描く彼の精神的な旅路が格好の事例である。
吾十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順う。七十にして心の欲する所に従いて、矩を踰えず。[2-4]
この簡潔な自伝体の手記は、多くの解釈を呼び起こした。明らかに、孔子は自分が学習者だとの自己認識に従って行動した。「十戸くらいの小さな村でも、私のように真心を尽くす誠意のある者はいるだろう。しかし、私ほど学問を好む者はいないだろう。」[5-28]
全人生を通じて、孔子は粘り強く自己を改善しようと試みた。聖人の頭巾を冠ったり、完全な道徳性を身に着けることは自分には不可能である。しかし、学習心は衰えることなく、人に教えることも飽きないことを完全に理解していた。[7-34]確かに、彼はあらゆる機会をとらえて学習することを求めた。「私を思いつきで二人からなるグループに仲間入りさせてごらん。彼らは、例外なしに私に教える何かを持っている。私は彼らの資質を模範として学ぶこともできるし、彼らの欠点を反面教師として学ぶこともできる。」[7-22]孔子は自らが賢くなるために、過去に蓄積されてきた知恵を獲得しなければならないことを正直に認めていた。「私は生まれながらに知識があった訳ではない。しかし、古代のことが気に入っていたので、私はすぐに古代を探し求めるのだ。」[7-20]さらに孔子は自己修養を怠ることを痛く心配していた。「徳力を磨くことを怠ること、学んだことの探求を怠ること、正しいと知っていることに力を貸せない、良くないことを改革できない。これが私の心配事なのだ。」[7-3]簡潔に言えば、孔子は「熱心に学習するあまり食事を忘れ、喜びの余り心配することも忘れ、歳を取ることにも無関心な」学習者だった。[7-19]
多次元的存在としての人間
孔子の学習内容は豊かで、多岐にわたる。論語では弟子の中には徳や雄弁、政治や文化で優れたものがいたと言われている。[11-3]これらは明らかに孔子の教えの科目ではなく、孔子の教育で特に尊重される民衆の隆盛を表す次元なのだ。おそらく孔子は、弟子たち皆が高潔で教養があり、雄弁で官職にコミットすることを望んでいた。しかし、彼らの中で最高にずば抜けていた者のみが、これら項目のどれかひとつで並外れた功績を示したのだった。通例として、孔子は彼の教育では四つの事柄を用いた。文、行、忠、信である。[7-25]正しく振る舞うことは、孔子の教授法では重要だったが、態度や信念が強調された。正しい態度や信念に基づかない正確な振る舞いは、堕落しやすい形式主義に過ぎない。確かに、あらゆる状況でどのように物事を見、話を聞き、人と話し、振る舞うかは、自己修養のまっとうな道ではあるが[16-10]、「断固とした態度、揺るがぬ決意、簡潔さ、沈黙を通してのみ我々は完全な人間性の実現が期待できる。」[13-27]事実、「礼儀正しさ、寛容、信頼、勤勉、慈愛」[17-6]という人間を社会的交わりに尽くさせることのできる五つの実践は、態度と振る舞いに関わるものでもある。
より広い文脈では、孔子の教えが倫理的な面に限られているわけではない。完全な人間になるために学習する総合的、統一的なプログラムとして、孔子の教育は今日我々が一般教養と呼ぶものの全範囲に及ぶ。儒教の六経は、全て包括的な人道主義ビジョンを象徴しており、そのビジョンは人間存在の詩的、音楽的、政治的、社会的、歴史的、形而上学的側面を包摂している。論語において、孔子は息子や弟子たちが儒教で使われる基本的言語や実践を学ぶため、まず、詩経と礼経から学習するよう説いている。孔子は書経で、堯、舜、禹三人の賢帝の人道的政治を賞賛し、それらに言及している。彼はまた、継続して易経を読むことで、人生で過ちを犯さないですんだとも述べている。さらに、彼の音楽に関する個人的経験と天命に対する暗黙の認識により、聴くという技能と、超越的存在に対する尊敬に基づいた人間の繁栄という実感を伝えることができたのだった。
このように、孔子の教育の根本は、人間は多面的な価値を持ち、多次元的存在だという強い信念である。還元主義者的思考は、物事を単純化してしまうばかりでなく、誤解を招く。我々はただ単に、理性的な動物でもなければ、道具を使ったり、言語を扱える存在でもない。何故なら、我々は美意識を持つ社会的、倫理的、精神的存在なのだからだ。我々が自身の肉体、心、魂、そして精神を大切にすれば、完全な自己実現ができるのである。我々が、絶え間なく広がり、ますます複雑になる社会関係に応じるために、自身の存在の中心から移動するとき、我々は自身の感性や意識の中で、家、地域社会、国家、世界、地球、宇宙を具現化する。これが、真の人間性とは相関的なものであり、対話的かつ心理的、精神的なものだと言われる所以なのである。教育はその出発点として、今この場にいる特定の人、根源的な結びつきを持った人、特に親子間の情緒的結びつきに深く根付いた人間を受け入れなければならない。
暗に近代主義者の見方では、人種、言語、性、地位、年齢、信仰などに基づく結びつきもまた関連性がある。ある意味では、特定の時間と空間に生きる我々は、かつて存在したことが無く、今後も二度と現れることのない独自の人間であることをそれぞれ運命づけられている。事実、我々は一人一人の顔が違うように、皆異なっている。しかし儒教徒たちは、我々の心と頭の共通性と伝達性が本質的には我々の本性を同じにし、それが視覚、聴覚、感情、意思、感覚、嗜好、経験を共有することを可能にすると信じている。この相違と相似の合流により、我々は、具体的に現存している人間になり得た根源的絆から切断されてはならない存在になり得るのだ。むしろ我々は、それらを自己実現のための道具に転換する。これが、個人的に独特で多くの知識や情報や知恵を他人と共有する多様な人々に出会うことで、学習者としての我々の人生が豊かになる理由である。さらに、我々の感情、欲望、動機、願望は個人的なものではあっても、私的なものである必要はない。我々はしばしば、縁者、友人、同志、仲間、そして見ず知らずの人にさえ強い個人的懸念を示す。彼らが、我々の内面的世界に対して同情と理解を示すことは、我々にとって深い意味のあることだ。
画一性無き調和
人生は多元的である。様々な人生体験を単に肉体的、心的、精神的次元に貶める試みは反生産的である。人間は本来、心理的、経済的、社会的、政治的、歴史的、美的、言語学的、文化的、形而上学的動物なのである。人間の潜在的可能性の完全なる実現は、決して一面的なものではない。孔子は、人間の隆盛を可能にする環境とは「画一性無き調和」だと信じていた。[13-23]差異に対する尊重が、健全な地域社会の発展にとって、決定的に重要なのである。
こうした考え方の中に潜んでいる孔子の倫理とは、究極的目的、純粋な動機、状況的妥当性、政治的関与、社会的責任、喜びに関するものなのだ。それは、我々が住んでいる世界全体を包摂し、人生の複雑な形式を前提としている。儒教の中核的価値は仁であり、それは、博愛、善良、慈悲、愛情など、さまざまな意味で表される。私は、陳榮捷の「人間性」という真っ直ぐな解釈がもっとも示唆に富み、説得力があると思っている。孔子にとって、人間性とは基本的位置を占める美徳であり、それはその他の全ての徳、すなわち正、義、礼、忠、信、智、仁、考を含む。人間性はまた、人間的優秀さ全ての具現化によって、豊かになり得る包括的な美徳でもある。長い間、孔子を研究する学者は、仁は必然的に社会的なものだと見なしてきた。何故なら、語源的に言えば、その漢字は人と二を示す漢字だからだ。優れた中国研究家のピーター・ブドバーグが、仁を読み解く適切な方法は「共有する人間性にある」と影響力のあるエッセイで主張したのは理解できる。(“The Semasiology of Some Primary Confucian Concepts”, Philosophy East and West 2, no. 4, 1953, 317―332.)
論語では、人間性は、往々にして智や礼と関連されたり、区別されたりしている。それは、特定の現存している人間の真実と現実を定義する内面的資質を示しているように思える。本物の学習とは「自己のために行い」、自立した自己修養と自己実現を通じてのみ、完成された人間に成り得るのだと孔子が見なしたのは、このためだったのかもしれない。儒教の伝統では、人はあらゆる関係の中心に位置し、それは、私的であると同時に社会的な存在でもある。郭店で見つかった竹簡に書かれてあった仁(人間性)は、二つの記号で描かれている。上には身、下には心である。このことが、人間性とは単に社会的なものだけではなく、深く個人的なことも意味することを生き生きと象徴している。
経済のグローバル化は、手段の合理性、科学、技術(特に情報とコミュニケーション技術)、テクノクラート管理、専門性、物質主義、欲望の解放と正当化、そして個人的選択によって特徴づけられている。「経済的人間」とは合理的動物で、自らの富・力・影響力の拡大に動機付けられ、法が治める自由市場で自己の利益を極大化しようと行動する利己主義を自覚している。「経済的人間」は、多くの近代主義的価値観を体現する。自由、合理性、権利、意識、仕事、倫理、知識、技術的能力、認識力、合法性、動機などである。しかし、社会的連帯に必要不可欠なその他の価値は、後ろに追いやられるか、完全に無視されている。とりわけ、正義、同情、責任、礼、そして倫理感などが、そうである。
物質主義的、利己主義的傾向といった特徴を持つ世界で、精神的満足に対する渇望は、往々にして、原理的過激主義や排他的党派主義の形式をとる。論語で述べられている孔子の人道主義は、人生の目的に対する調和のとれた、開かれた取り組みである。それは、自己認識にとって不可欠な精神的修行を提供し、人間の自己認識にとって永遠に有意義で根源的な知恵とインスピレーションの源になるのである。